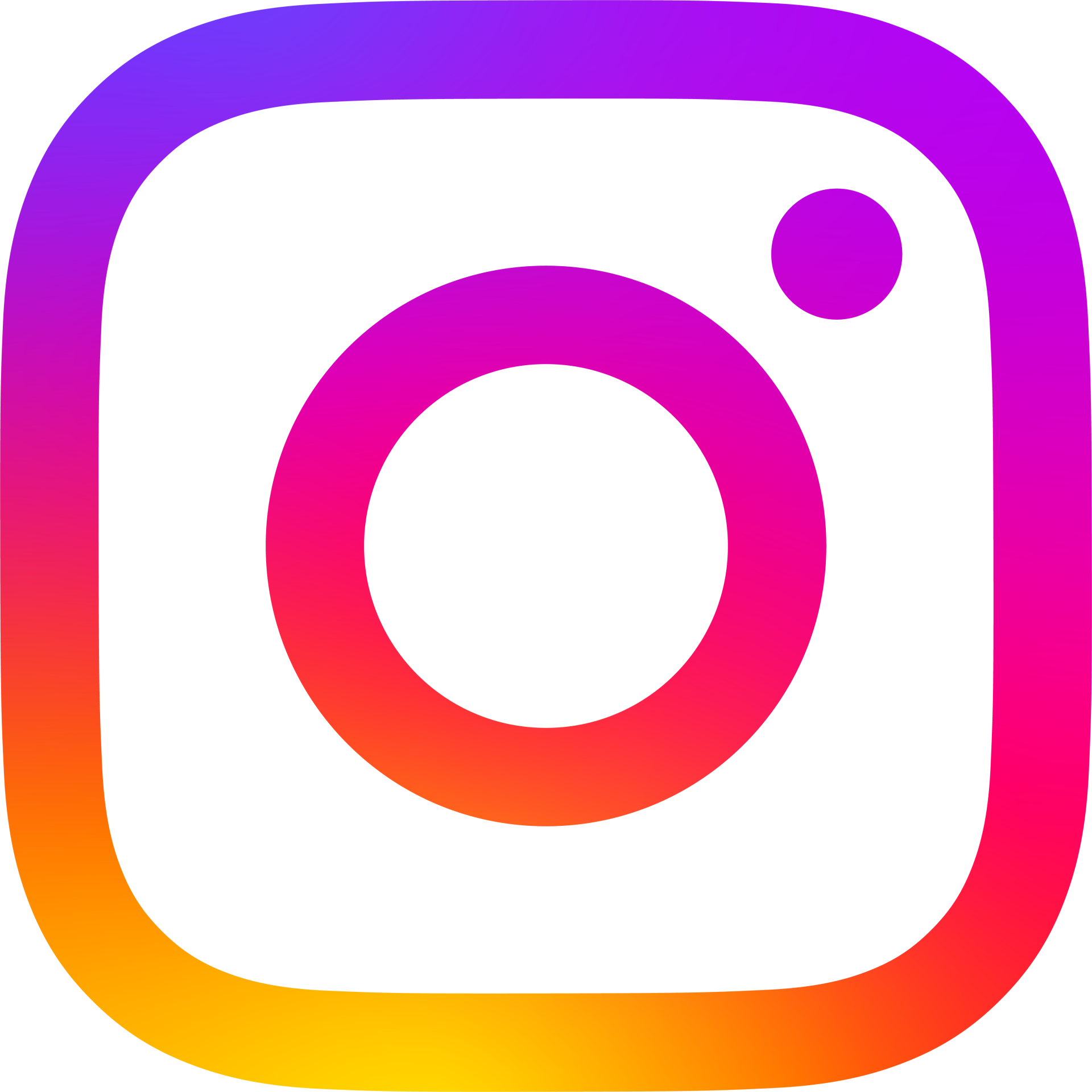【蓮見聖都の造り手の舞台裏】収穫編
体験ではなく、1日目から最終日まで仕事を共にした収穫のお話。
今回は、ブドウの収穫のお話です。1日や数時間だけの「体験」ではなく、
収穫の1日目から最終日まで。私は去年、生産者と共に仕事として収穫をしてきたので実際のお話をお伝えできればと思います。
実際に収穫をした場所は、フォジェールとシャサーニュ・モンラッシェ。
初日から最終日まで収穫をしたのは、シャサーニュ・モンラッシェなので、メインはこちらの話になります。
ブドウの収穫は、例年9月の第2週頃から始まりますが、南フランスのフォジェールなど、フランスでも暖かいエリアは8月末頃から始まります。逆にシャンパーニュなど北のエリアはもう少し後から。
収穫にかかる日数、エリアは生産者によって異なり、フォジェールでは1ヶ月。
シャサーニュ・モンラッシェでは9日間で全てのブドウ畑を収穫します。
収穫の仕方は、手摘みと機械の2パターンありますが、今回参加した収穫は全て手摘み。
勿論、両方の収穫方法にメリット・デメリットはあるのですが、手摘みの何よりの1番のメリットは、ブドウを傷つける事なく収穫することができ、ブドウを収穫し、プレス機で果汁を搾り出す瞬間から管理できる。という事。
デメリットは、とにかく時間がかかり、体力仕事だという事ですが、、
一緒に収穫を行ったシャサーニュ・モンラッシェの生産者、ローラン・ピヨでは、
9日間、毎日朝6時に集まり、解散するのは夜中の23時。これを9日間毎日です。
今思えば、よく体調を崩さずやり切ったと我ながら思います、、、
ドメーヌに5時半ごろから集まり、パンとコーヒーを食べ、朝日と共に収穫を開始します。小休憩でサンドイッチを食べ、再び収穫。暗くなる前にその日のブドウをドメーヌに運び、プレスをし、ステンレスタンクへ。作業が終わり次第、夜ご飯を集まって食べて解散します。大体のスケジュールはこのような感じです。
手でブドウを収穫と言っても、ただハサミで切って回るのではなく、なかなかハードな作業です。
ブドウがある位置は膝の辺りなので、まず膝立ちになります。地面は土よりも石灰岩などのごつごつした石の方が多いので、かなり痛いです。
収穫したブドウを小さいバケツに入れ、いっぱいになったらトラックまで運搬する人にパスをし、新しいバケツを受け取る。この時、かなりの頻度で、立ち座りをするので腰もなかなかしんどい。
「このワインは手摘みで収穫されたもの」と一言で言っても、ここまでの苦労があるのかと実際に働いて初めて痛感しました。
ハスミワインのシャサーニュ・モンラッシェの生産者は「ローラン・ピヨ」ですが、生産者の中でも頭ひとつ抜けての細かさ。
その日、収穫で使用した、バケツ・ハサミ・プレス機やブドウを運搬する機械、タワシやモップなど。とにかくその日に使用した「物」全てを完璧に掃除をし、元あった場所に戻します。たとえそれが3時間後に再び使用する物でも、一見ワインとは直接関係のなさそうな物に見えても。丁寧に綺麗にし、片付けをします。
彼が頭ひとつ抜けて細部まで綺麗にしていますが、基本ハスミワインの生産者は細かく気にする人たちです。
美しく生きるということは最も厳しく生きること。それが自分たちの造るワインに現れる。
その言葉を聞くと、改めて彼らのワインをハスミワインで輸入できていること。日本において、彼らのワインを使ってもらっているということに感謝です。
そんな彼らの想いや、仕事ぶり。美しく生きる生産者たちが造ったワイン。是非飲んでみてください。









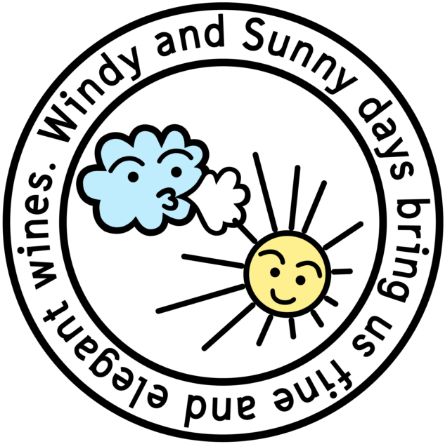








 フランス
フランス スイス
スイス オーストリア
オーストリア デンマーク
デンマーク